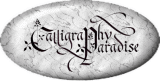初心者のためのカリグラフィー講座 Calligraphy Paradise
フラクチャー体基本練習fraktur
フラクチャー体について
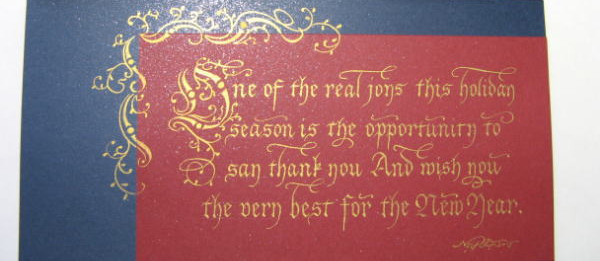
ゴシック体の仲間に入りますが、16世紀後半ドイツで生まれた書体です。
いわゆる北方ルネサンスの産物です。
現在イタリック体と呼ばれる、イタリアを中心に発達した書体と並んで
この時代の代表的な書体と言っていいと思います。
| 基礎練習1・2 ”a”〜e” |
| ”f”〜”l” |
| "m"〜"r" |
| "s"〜"z" |
| 大文字”A”〜”H” |
| 大文字”I”〜”P” |
| 大文字”Q”〜”Z” |
ゴシック体との違い
”Calligraphy”という単語を並べてみました。パッと目似てるような似てないような。【ゴシック体】
【フラクチャー体】
練習時の大きな違いが2つあります。
1.ウエストラインの考え方
ゴシック体では各文字の菱形右角を揃えるためのラインでした。
フラクチャー体では各文字の天辺を揃えるためのラインです。
2.菱形の書き方
ゴシック体ではとにかく鋭角にこだわり、菱形も整った形が必要でした。
しかし、フラクチャー体での菱形は若干湾曲しています。
ペン先の角度が45度という点はゴシック体と同じです。
教室によっては40度かと思います。
基本練習
アッセンダー ペン先2つ半Xハイト 〃 5つ
ディッセンダー 〃 2つ半
【基本練習1】
”i”です。上下の菱形がフラクチャー体の特徴です。
ゴシック体にくらべ、横長で湾曲しています。
ウエストラインのペン先1つ分下にペン先を45度におき、下方へ湾曲した菱形をつくります。
垂直にペンを降ろします。
上方が湾曲した菱形をつくります。
動きの基本はゴシック体の"i"と同じです。赤いラインの軌道をつくります。
最後に”i”の点としてアッセンダー内に緩くカーブしたラインを書きます。
【基本練習2】
”o”です。
書き順1は"a,c,e,g,q"で、書き順2は"b,,p,v,w,y"で必要な動きです。
"o"が書ければこれらのアルファベットもかなり楽に書けます。
書き順1 ウエストラインを始点とし、左側に軽くカーブしたら、垂直に降ります。
ベースラインよりペン先1個半あたりで右へ曲がります。
書き順2 書き順1の始点にペン先を重ね、緩く右へ張り出しながら書き順1の終点に向かって降りていきます。
※ 書き慣れるまでカーブの膨らまし具合に迷うところですが、書きあがったとき、45度の空間(▲)が
きちんと残るよう、まずは気をつけてみて下さい。
アルファベット順
【a】
書き順1 "o"の書き順1参照。
書き順2 ウエストラインから右斜めに降りてから書き順1と同じ書き方をします。
※ ”a”の下半分だけ見ると同じ形になります。
【b】
書き順1 アッセンダーラインから細いラインを出しながら垂直に降り、右へ大きく張り出した菱形をつくります。
書き順2 ”o”の書き順2参照。"o"より先を尖らせて下さい。
【c】
書き順1 ”o”の書き順1参照。
書き順2 書き順1の始点に重ねて図のようにカーブします。
※ 終点の位置に気をつけないと、”e”と区別がつかなくなります。
【d】
書き順1 書き出しは”o”の書き順1と同じですが、”b”の書き順1と同じ長い菱形を書きます。
書き順2 アッセンダーラインを始点とし、左にカーブしてからxハイト内に入ります。後は”o”の書き順2と同様の緩い
カーブをつくり、書き順1の終点に合わせます。
【e】
”e”です。
書き順1 ”o”の書き順1参照。
書き順2 ”c”の書き順2と似ていますが、終点を書き順1の垂直線にきちんとつけます。
※ 右側の”e”のように、書き順1の終点で菱形をつくっても良いです。