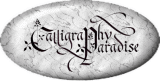初心者のためのカリグラフィー講座 Calligraphy Paradise
ゴシック体Gothic
ゴシック体 大文字基本練習&”A"〜”E"
| 小文字 1ページめ 基本形(i,j) 基本形・バリエーション1(n,m,r,x) 基本形・バリエーション2(u,y) 基本形バリエーション3(a,c,d,e,g,q、f) |
| 小文字 2ページめ 基本形・バリエーション4(l、h、k) 基本形・バリエーション5・6(b) 基本形・バリエーション6続き(o、p、v、w) その他(s、t、z) |
| ゴシック体の数字 |
| 当ページは大文字 基本練習&”A”〜”E” 大文字 ”F”〜”L” 大文字 ”M”〜”S” 大文字 ”T”〜”Z” |
ゴシック体大文字 基本練習
【基本練習1】
左端の形をみて下さい。”J”の大文字です。
この形は2つポイントがあります。
書き順1・2でつくる角と2つに並んだ縦ラインです。
まず書き順です。
書き順1 ウエストラインの少し上からペン先45度でくちばしの形に似た角をつくります。
書き順2 書き順1の始点と重ねながらまっすぐ降ろし、ディッセンダーで細いラインを出します。
書き順3 始点は書き順1に覆い被さるように始めます。
終点は書き順2の終点よりほんの少し短くします。縦ラインよりも横ラインがかなり細くなります。
書き順1・2の角ですが、最初は書きにくいかもしれません。
中に空白ができたり、きちんと重なり合わなかったりするかもしれません。
ですが、この書き方は他の書体でも使うので(アンシャル体やブックハンド体など)、
今ここで練習しておくことをお勧めします(セリフのお話参照)。
もう1つ、縦ラインの2本組はゴシック体大文字で頻繁に使います。必ず右側のラインがほんの少し短いのが
特徴です。この2本の間ですが、狭すぎも良くないですが、空きすぎもまとまりがなくなります。
縦ラインの太さ半分〜3分の1ぐらいを空けるつもりで練習してみて下さい。
【基本練習2】
”O”です。”O”の中に縦ラインが入っているのがゴシック体らしいです。
書き順1
アッセンダーラインから垂直に降り、縦ラインの終点はベースラインよりペン先1つ以上短くしておいて下さい。
書き順2
書き順1の始点にペンを重ね、左円を描きます。
書き順3
書き順1の始点と同じ位置からですが、ちょっとだけ細いラインをだしてから
アッセンダー〜Xハイトを使って右円を描きます。
終点で書き順2の終点と細いラインでつながるよう丸みに気をつけて下さい。
※この書き順2・3の円は他のゴシック体大文字でもたくさん使います。
ガイドラインをはみ出さずに”○”がかけるよう練習して下さい。
書き順1の縦ラインが長すぎると、円も大きくなります。要注意!
基本練習1と2をこなせば、おおかたのゴシック体大文字は楽勝(?)です。
さっそく”A”からトライしてみましょう!
【A】
書き順1
アッセンダーラインの少し下から左へ柔らかく張り出します。終点は鋭角にゴシック体らしく。
書き順2
始点は書き順1を覆い被す位置からです。横ラインを水平引いたら直角に曲がって縦ラインを降ろします。
書き順3
Xハイト上3分の1ぐらいから横ラインを引きます。
【B】
書き順1
まず菱形を作ってから垂直に降り、左に鋭角に張り出してからベースラインに向かって斜めに降ろします。
終点は右斜めに細いラインを持ち上げて下さい。
書き順2
斜めの細いラインを上下に持つ縦ラインを引きます。
書き順3
”B”の右側を書きます。おのおのの角を鋭く作って下さい。
※ 書き順1の始点ですが、細いラインは出しても出さなくても良いです。
最初に細いラインを出すとペンの滑り出しが良く鋭角な菱形をつくれるのでゴシック体では好まれる書き方ですが、
いきなり菱形を書き出しても、もちろん問題ありません。他の大文字・小文字でも同様です。
ただし、大文字の菱形は小文字より横長になります。
これ以降の説明でも同じ部位でもこの細いラインを説明している文字とそうでない文字がありますが、
私が書いてみて細いラインを出した方が結果的にきれいに書きやすい文字について特に説明しています。
【C】
書き順1・2 縦ラインを先に2本引きます。そのとき書き順2の方を少し短くします。
書き順3 縦ラインを包むように半円を書きます。
書き順4 ”C”らしさを出すために右側の縦ラインに短いひげをつけて下さい。
【D】
書き順1 ウエストラインの少し上からくちばしの形を書きます。
書き順2 書き順1に重ね、垂直に降り、左に鋭角に張り出してからベースラインに向かって斜めに降ろします。
終点は右斜めに細いラインを持ち上げて下さい
書き順3 上下に細いラインを出した縦ラインを引きます。
※ 書き順2に触れないように
書き順4 全体を覆い被すように頭をつくります。横ラインはしっかり水平にして下さい。
最後に書き順2の終点と書き順4の終点が細いラインで繋がります。
【E】
”C”に書き順5の水平線が加わった形です。
ウエストラインより少し下に引くようにして下さい。